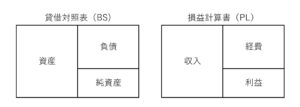料金や報酬に源泉徴収が必要かどうかの調べ方
料金や報酬には、多岐にわたるものが含まれ、源泉徴収の判断もむずかしいものがあります。
とりあえず、国税庁が公表している「源泉徴収のあらまし」をあたってみましょう。
源泉徴収は義務
個人のかたへ料金などの支払いをするときは、源泉徴収が必要なことがあります。
その源泉徴収とは、所得税の天引きのこと。
たとえば支払いが「10万円」のとき、「1万円くらい」を源泉徴収し、残りの「9万円くらい」を相手にわたすことになる。
つまり、その所得税は、相手の税金なわけです。
そして、その源泉徴収した所得税は、原則として支払いをした月の翌月10日までに、自分で納付書をつくり、税務署へ払わなければなりません。
面倒ですよね。
でも、これは支払いをする側の義務なのです。
(常時2人以下の家事使用人しかいない個人事業主は、義務ではありません)
義務にされているのは、税務署が税金を取りはぐれないようにするためかもしれません。
ただ厄介なのは、源泉徴収を忘れたときに「相手から取ってくれ」とは言えないこと。
これが、義務という言葉があらわす意味なのです。
きっと、役員報酬や給与から源泉徴収することは、ご存じのかたも多いですよね。
でも、料金や報酬については、いろんな種類にわかれていて、判断がむずかしいものも多いです。
税理士のわたしだって、そのつど調べなければ分からないくらい。
その調べ方を確認しておきましょう。
どう調べるか
おススメしているのは、国税庁が毎年公表している「源泉徴収のあらまし」という小冊子です。
インターネットで検索すれば、きっと出てきますよ。
(もし紙のものが欲しければ、年末調整の時期に税務署へ行くと、置いてあるかもしれません)
おそらくネットの検索画面では、こんな風に。

それをクリックしたら、「報酬・料金等の源泉徴収事務」を開いてみましょう。

するとPDFが開かれ、こんな感じのものが。
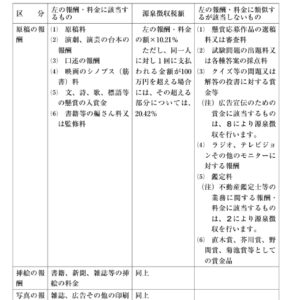
支払いの内容が、うえの資料のどれに当てはまるか…?
源泉徴収が必要かどうかは、こんな風に判断していくのです。
気をつけたいのは、相手の肩書きで判断するのではない…ということ。
あくまでも、内容によって判断するのです。
だから、たとえば相手が士業であっても、まったく関係のないモノを買ったときの支払いなら、源泉徴収は必要ありません。
また、支払いの名目が、料金や報酬ではなく、交通費や取材費などであっても、実費精算ではなく実質的には仕事への支払いなら、源泉徴収は必要になります。
この源泉徴収が必要かどうかは、相手が知らないこともままあります。
そんなときでも、支払う側にとっては義務。
それを怠れば、税務署から「払ってね」と言われるのは自分です。
相手まかせにせず、自分でも裏をとるようにしておいたほうが安全なのです。
納期の特例をつかっているなら
料金や報酬から源泉徴収したものも、「一部」は納期の特例がつかえます。
その「一部」とは、弁護士や税理士などの士業へのもの。
正確には、源泉徴収のあらましにて、第204条第1項「第2号」にあるものです。
たとえば、原稿料やデザイン料・講演料などは、納期の特例がつかえません。
原則どおり、支払った月の翌月10日が期限になるのです。
これらは、「第2号」にふくまれるものではないので。
料金や報酬は、第1号~第8号にわかれています。
そのうち、どの「号」にあたるのかも、気をつけるようにしましょう。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。