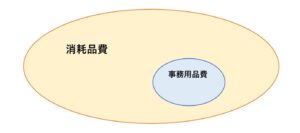株式会社と合同会社の違い、選ぶときのポイント
株式会社と合同会社の違い、選ぶときのポイントについて解説します。
周りあっての商売なので、自分の気持ちにくわえて周りの反応もみてみたいところです。
目次
株式会社と合同会社の違い
まずは株式会社と合同会社の違いを表でみてみましょう。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
| 会社の持ち主 | 株主 | 社員 |
| 会社を経営する人 | 取締役 | 社員 |
| 持ち主と経営者の関係 | 異なる | 同じ |
| 会社の意思決定 | 株主総会 | 社員総会 |
| 設立時の費用 | 約25万円 | 約10万円 |
| 決算公告 | 義務 | 義務ではない |
| 役員の任期 | 最長10年 | 無期限 |
| 会社の代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
| 配当金 | 出資割合におうじる | 出資割合によらず自由に決めてもよい |
| 上場 | できる | できない |
| 税金 | どちらも同じ | |
では、それぞれについて補足していきますね。
会社の持ち主
会社の持ち主は次のとおりです。
- 株式会社……株主
- 合同会社……社員
ともに会社に出資をした人をあらわす言葉です。
出資者は出資のみかえりに、株式会社なら「株式」を、合同会社なら「持分」を手にします。
気をつけたいのは、株主や社員が亡くなったときのことです。
株式は相続することができますが、持分は基本的には相続できません。
そのため、もし一人で合同会社をつくったようなときは、亡くなったときに会社が清算されてしまうことになってしまいます。
ただし、このルールは定款に「社員が死亡したときは、相続人がその社員の持分を承継する」という規定をつくっておくことで回避できます。
- 自分一代で会社はたたむ。
- 将来は誰かに引き継いでほしい。
このようなことは会社を設立したときには未定のことも多いので、万が一のことをかんがえて合同会社の定款をつくっておきましょう。
会社を経営する人・持ち主と経営者の関係
株式会社の経営は、株主ではなく取締役がおこないます。
いっぽう合同会社の経営は、出資をした社員みずからがおこないます。
出資をするひと・経営するひと。
これらが分かれているか・同じなのか、に違いがあるのです。
なお、合同会社に出資をしても経営にかかわらないことはできますが、その逆はできません。
合同会社の経営にかかわりたいなら、出資をしなければならないことに気をつけましょう。
会社の意思決定
会社にとって大事なことは、株式会社なら「株主総会」で、合同会社なら「社員総会」で決めます。
もし多くのひとが会社に出資をしたときは、次の理由でスピード感が変わります。
- 株式会社……経営にかかわらない株主もいる
- 合同会社……基本的に社員はすべて経営にかかわる
また、いろいろな意見があるときは多数決で決めますが、次のように議決権の持ちかたが違います。
- 株式会社……出資した金額におうじて議決権をもつ
- 合同会社……出資した金額にかかわらず1人1つの議決権をもつ
株式会社をつくって自分の意見を出したいなら、それを見据えて「いくら出資するか」を考えましょう。
2人で合同会社をつくり意見が割れたときは、永遠に平行線とならないように気をつかいましょう。
株式会社・合同会社ともに複数人でつくるなら、ここまでを踏まえて「誰が・いくら出資するか」の検討が必要です。
設立時の費用
会社の設立費用は、次のとおりです。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
| 定款に必要な印紙 | 4万円(電子定款なら不要) | |
| 定款認証の費用 | 資本金100万円未満……3万円 資本金100万円以上300万円未満……4万円 資本金300万円以上……5万円 | 不要 |
| 登録免許税 | 資本金の0.7% (最低でも15万円) | 資本金の0.7% (最低でも6万円) |
| 合計 | 約25万円 | 約10万円 |
決算公告
株式会社は、毎期の決算を公告しなければならないというルールになっています。
官報や新聞、自社ホームページなどに決算書を載せなければならないのです。
もし公告しないときは「100万円以下の過料」という罰金がかかります。
ただ、これまで実際に罰金を払ったということを聞いたことはありません。
おそらくですが「官報に決算公告するのに10万円前後のお金がかかるため」、罰金を科すところまでは踏みこんでこないのかもしれません。
ただし、今後のあつかいがどのように変わるかは保証がないので、気にしておく必要はあるでしょう。
いつでも対応できるように自社ホームページをもっておくなどして。
なお、合同会社は決算公告をしなくてもよいので楽ですね。
役員の任期
株式会社の役員には任期がありますが、合同会社にはありません。
役員は任期がきたら、再任や変更の登記をしなければなりません。
そのたびに数万円くらいの費用がかかります。
この費用を抑えるために任期を長くしたときは、「忘れる」という問題がおこります。
任期は最長で10年ですので、忘れることも十分ありえます。
任期がきたことを忘れたまま放置していると、裁判所や法務局から手紙が届いてしまいます。
「登記をしなさい」と。
場合によっては罰金まで払うはめになります。
この手紙まで放置しておくと、法務局により「みなし解散」されてしまいます。
「もう通常の営業はしていない会社」と登記簿にも載ってしまうのです。
また、もとの状態にもどすために、さらなるお金が出ていくことにもなります。
役員の任期というのは、何年にするかもふくめて地味に気をつかうものなのです。
会社の代表者
会社の代表者の肩書は、次のとおりです。
- 株式会社……代表取締役
- 合同会社……代表社員
名刺をつくるときに取り違わないように気をつけましょう。
配当金
株式会社が配当をするときは「1株あたり○○円」となるので、出資におうじた金額となります。
いっぽう合同会社の配当は、出資におうじない金額にすることもできます。
配当金は、税引き後の利益を分配するものであり、経費にはなりません。
そのため、中小企業では敬遠されがちなところもあります。
こんな違いもあるんだね、ということで聞いておいてくださいね。
上場
合同会社は株式上場することができません。
そのため、多くのひとから出資をあつめて会社を大きくしていきたいときは、株式会社を選びましょう。
税金
会社を設立したあとの法人税などの税金に違いはありません。
節税手法についても、どちらを選んでも同じ方法をつかっていくことになります。
では、引きつづき株式会社・合同会社を選ぶときのポイントをみていきましょう。
選ぶときのポイント
株式会社か合同会社を選ぶときは、これまで書いてきたことに加え、次のことも検討しましょう。
- 知名度
- 経営における手間
- 事業展開
- 相続や事業の引き継ぎ
- どちらかに変えたくなったとき
知名度
最近は合同会社もふえてきましたが、それでも知名度は株式会社のほうが上です。
個人的には、今後も合同会社はふえていくと思います。
気をつけるポイントさえ押さえておけば、合同会社は身軽ですし手間もかからないからです。
ただし、第三者からみたときにどう思われるかが問題となるときもあります。
知名度がひくいということは、「大丈夫かな?」と見られることもあるわけなので。
たとえば人材採用やそれぞれの業種・業界ごとの「多数派」の意見です。
また、社長といえば「代表取締役」というのは本やテレビなどでも一般的でしょう。
名刺を見せたときに「?」となってほしくない。
ちょっと気おくれしてしまう。
こんな風に感じるなら、株式会社を選びましょう。
気持ちの問題も重要ですから。
ちなみに、AmazonやGoogle、appleの日本法人は合同会社ですし、西友も合同会社です。(豆知識)
経営における手間
決算公告や役員の任期をかんがえなくてよい分、合同会社のほうが手間がかかりません。
これらは法律上のルールなので、やらなければ罰金もかかります。
手間にくわえてお金も出ていくのです。
事業展開
会社を大きくしたいと考えるなら、株式会社のほうが有利です。
合同会社でもできないことはないですが、上場できなかったり知名度の点で、現時点ではハンデを負っています。
相続や事業の引き継ぎ
相続や事業を誰かに引き継いでもらうことを考えると、株式会社のほうがやりやすいです。
こまかい点はいくつもありますが、合同会社での相続や事業の引き継ぎをスムーズにすすめるには、株式会社以上に「事前にしっかり準備する」ことを覚えておきましょう。
どちらかに変えたくなったとき
いちど会社をつくったあとでも、次のように変更することはできます。
- 株式会社を合同会社に変更
- 合同会社を株式会社に変更
ただし、いまの会社を清算して別の会社をつくるという手続きを踏むことになります。
手間もお金もかかりますし、名刺やチラシ・書類など前の会社名がはいっているものをすべて取り替える作業も必要です。
まとめ
株式会社と合同会社の違い、選ぶときのポイントについて解説しました。
商品やサービス・人・数字など中味で勝負するのが本筋だとは思うのですが、「他の人がみてどう思うか」ということが気になるのも分かります。
周りの人あっての事業ですので。
自分の気持ちを軸に、周りの人の反応もすこしみてみましょう。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。