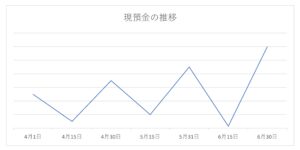「役員報酬はいくらがよい?」の答え
最終的には「社長の好きなだけ」でよいと考えています。
ただ、その前に検討すべきことを確認しておきましょう。
目次
役員報酬はいくらがよいか
役員報酬を決めるのは、とても悩むものです。
というのも、役員報酬を変更できるのは、基本的には年に1回。
それも、年度がはじまってから3か月以内まで…という縛りがあるからです。
そして、変更の前・後は、それぞれ毎月がおなじ金額でなければなりません。
そうでないと、経費にはならない部分がでてきてしまうので。
なので、いろんなことを考え、かつ、今期はどうなりそうか…と先を見ることも必要です。
役員報酬は、経費のなかでも大きな金額になるので、利益への影響も大きいので。
ただ、最終的には「社長の好きに決めていい」と考えています。
もちろん、いくつか検討して欲しいこともありますが。
それが何なのかを確認していきましょう。
役員報酬を考えるときに検討すべきこと
検討すべきなのは、次のことです。
- 会社の税金、個人の税金
- 法人税法の縛り
- 家族の給与
- 退職金
- 社会保険
- 自社の株価
- 融資
- 会社と役員のお金の貸し借り
会社の税金、個人の税金
自分で会社をつくり、自分で経営をするなら、会社も個人も財布はおなじような感覚になるものです。
そして、それは税金もおなじ。
こんなときは、会社・個人あわせたトータルの税金がすくなくなるように…という視点で考えます。
会社の税金(消費税をのぞく)は、利益のだいたい30%ほどです。
いっぽう、個人のほう(所得税)は、税率が5%~45%と幅があります。
そのため、役員報酬によっては、トータルの税金が変わってくるのです。
このとき、いちばん税金がすくなくなるポイントを考えるかどうか。
もちろん、利益は見込みで考えるので、結果は年度が終わってみなければ分かりません。
そのほか、会社で将来の設備投資などにそなえておく必要があるか、役員のプライベートはどうか、といったことも影響してきます。
ただ、個人の税金を計算するとき、役員報酬からは「給与所得控除」という経費をひくことができます。
役員として働けば、交通費や交際費のようなもろもろの出費がでてくるからです。
こうした出費をカバーするためのものが、給与所得控除なのです。
この給与所得控除は、役員報酬の金額におうじて、自動的にきまります。
実際にかかった出費を集計する必要はないのです。
いわば、領収書のいらない経費といえます。
この給与所得控除と、会社・個人の税率差により、トータルの税金の最適解をさがす。
とても頭をひねりますが、これは王道の節税方法なのです。
法人税法の縛り
役員報酬には、仕事にみあった金額でなければならない…という縛りもあります。
不相当に高額なときは、その不相当な部分が経費にならないのです。
ただ、実際に「相当な」金額をわりだすのは、困難です。
働きかたや置かれている環境により、「相当」は変わるべきものです。
くわえて、役員報酬にかんするデータで、信頼がおけるものが、あまり出回ってはいないので。
そのため、普段はあまり話題になることもありません。
もし興味があったら、国税庁が公表している「民間給与実態統計調査」を見てみるのもよいです。
ひとつ、役員報酬は、株主総会できめます。
そのときの議事録に載せた金額は、超えないようにしましょう。
もし超えていれば、それは明らかに不相当に高額ですから。
…と、ここまでのことを、頭の片隅においておきましょう。
家族の給与
家族と一緒に経営していれば、その家族にも給与をだします。
家族が役員なら、役員報酬を。
このとき、世帯全体の税金を考えることもあります。
その最適解は、「全員がおなじ金額の役員報酬または給与」です。
でも、社会保険(健康保険・厚生年金)を加味すると、変わる可能性もあります。
税金よりも、社会保険のほうが高いこともあるので。
扶養になれるほうが、税金・社会保険のトータルが少なくなることもあるのです。
(将来もらえる年金を考慮すると、更にややここしくなります…)
また、家族への給与にも、仕事にみあった金額でなければならない…という縛りがあります。
たとえば、夫婦ともにおなじ金額の役員報酬だとしてみましょう。
それが、税金の最適解なので。
でもこれは、ふたりとも社長のような状況でなければならない…ということでもあるのです。
おそらく、難しいのではないでしょうか。
ここまでを踏まえて、家族の給与にかかる税金、そして社会保険も忘れないようにしましょう。
退職金
役員が会社を辞めるときは、退職金をもらうことができます。
たとえ、自分の会社であっても。
この退職金は、税金がとても優遇されています。
おなじ金額を役員報酬としてもらうことに比べれば、100万円単位の節税になることも珍しくないのです。
ただ、退職金にも、不相当に高額な部分は経費にならない…という縛りがあります。
この縛りをめぐっては、相当なのか不相当なのか、たくさんの判例もあります。
退職金自体が目を引くうえに、金額も大きくなりがちなので、揉めるタネなのです。
そこで実務では、次の算式で「相当」な金額を割り出すことも一般的です。
- 退職直前の役員報酬 × 役員在任年数 × 功績倍率
(注)功績倍率は、1.0~3.0が一般的
つまり、会社を辞めるときの役員報酬をベースに、退職金を決めることが多いのです。
そして、辞めると決めてから、とつぜん役員報酬を上げても、通らなかったりもします。
見え見えですから…
普段の役員報酬が少なければ、退職金も少なくなるかもしれないことを知っておきましょう。
社会保険
役員報酬の金額によっては、税金よりも社会保険のほうが高いです。
金額によっては…というのは、社会保険には上限があるからです。
その上限を毎月の役員報酬におきかえれば、今のところ東京都ではつぎのとおり。(協会けんぽ)
- 健康保険……約136万円
- 厚生年金……約64万円
役員報酬を、これ以上とっても、社会保険は変わらないのです。
役員報酬を決めるときには、社会保険の影響も大きいことを知っておきましょう。
自社の株価
自分で会社をつくるときは、資本金をだす代わりに、自分の会社の株式をもらうことになります。
おそらく紙で株式をつくることはないと思いますので、目には見えません。
でも、株式を持っていることは意識しましょう。
というのも、株式も値段のつく財産だからです。
そして、売買や贈与・相続の対象にもなります。
つまり、所得税や贈与税・相続税が、将来かかってくるのです。
これらの税金は、株式の値段によって変わります。
そして、株式の値段は、会社の業績におうじて変動していきます。
黒字になれば値段もあがり、赤字になれば、その逆と。
もし、値段が高くなれば、税金だって高くなってしまうのです。
…ということが、将来の悩みのタネになるかもしれません。
そこで、株式の値段を下げるために、役員報酬の設定を検討することもあります。
株式の値段は、急には変えることができません。
数年かけるくらいの気構えが、必要なこともあるのです。
もし、お子さんが会社を継ぐかもしれない…というときは、このことも念頭においておきましょう。
融資
融資を受けるなら、とうぜん返さなければなりません。
そのため、金融機関は「返せるか…」ということは常にチェックしています。
おもに、利益がちゃんと出ているか…ということから。
こんなときは、どうしても黒字にしたくなるものです。
そこで、役員報酬を極端に少なくしてしまう…という誘惑がでてきます。
でも、少ない役員報酬で生活はできるのか…ということも、金融機関はみてきます。
貸したお金が、役員のプライベートにつかわれないか…と。
もしそうなら、貸す意味がないですから。
自分でつくった会社なら、自分で役員報酬を決めることができます。
でも、役員報酬に惑わされずに、利益を考えるようにしましょう。
会社がピンチのときは、社長個人のお金を流用するはずです。
役員報酬とは、仮の数字のようなもの…と捉えておきましょう。
会社と役員のお金の貸し借り
自分あるいは家族で会社を経営していると、お金は一緒くたになりがちです。
会社のお金・個人のお金をキッチリわけるのには、そうとう神経をつかうし、ハッキリいって面倒ですから。
そこで、会社の会計データには、「役員への貸付金」や「役員からの借入金」が登場してきます。
たとえば、社長が会社の経費を立て替えたのなら、それは会社にとって「役員からの借入金」です。
気をつけたいのは、こうした貸し借りが累積していく…ということ。
気がついたら3ケタ万円になっていることも、珍しくないのです。
ただ、これらは、いつかは精算しなければなりません。
そのために、役員報酬を調整することも、候補の一つです。
もし役員が、会社からお金を借りているなら、返すための原資を考慮して、おおめに役員報酬をとる…といった風に。
あまりにも貸し借りが積み重なっていかないように、貸借対照表をチェックしておきましょう。
まとめ
役員報酬はいくらがよいか…を検討する材料を確認してきました。
最終的には、「社長が欲しいだけ」でよいと思っています。
でも、その前に検討すべきことがたくさんあるんだな…ということは知っておきましょう。
もちろん、頑張れば頑張っただけ増えるということも。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。