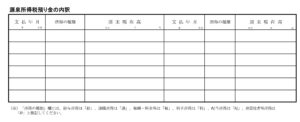ものの値段に惑わされないようにするには
高いものをみると、「良いものなんだろうな」と思ってしまうものです。
それは、お金に惑わされているのかもしれません。
ものの価値は自分で決める…と意識してみましょう。
値段が惑わす
お金には、すくなくとも次の3つの機能があります。
- モノやサービスと交換できる
- ものの価値をあらわす尺度
- 貯めておける
このうち、ものの価値をあらわす尺度としての機能には、気を付けたいことがあります。
それが、「高いものは良いものか」ということ。
お金って、手に入れるのは難しいですよね。
だから、高いものは、そう簡単に買えるものではない。
ということがあるから、憧れのようなものも含めて、高いものは良い…と錯覚しがちです。
手にいれるのが難しいから、余計に手に入れたくなる…ということもありますしね。
でも、たとえば魚や野菜など。
これらは、不漁または不作のときほど高くなります。
需要と供給のバランスがありますからね。
そしてなぜか、そういう時ほど栄養もすくなかったりします。
- 高いのに、痩せてて栄養がすくない
- 安いけど、脂がのっていたり旬だったりして栄養はおおい
このように、値段と質は反比例するようなこともあるわけです。
こんなときでも、「高いものは良い」と言えるでしょうか。
高いものは良いと思ってしまうことは、ある意味、お金に惑わされていると言えます。
お金を手に入れることの難しさが、ものの価値の判断を狂わせている…と。
そうなると、お金の使いかたにも影響がでてきます。
そう惑わされないようにするには、どうすればよいのでしょうか。
惑わされないためには
ものの価値は、人それぞれ受け取りかたが違うものです。
だから、値段も人それぞれ違ってよいのかもしれませんね。
でも、そんなことを言ってしまえば、市場は大混乱。
1つ売るたびに、値段交渉をしなければならないでしょうし。
ただ、お金はモノやサービスと交換するためのもの。
そのモノやサービスをつかって、自分が何を得て、どんな風に変わるか。
それが、本来つけるべき値段といえます。あくまで自分目線ですけれどね。
高いものは良い…というのは、お金自体が基準になっているのかもしれません。
お金以外に基準をもっているか、考えてみましょう。
そちらから、値段の妥当性を考えるのです。
そして、とくに事業をしている場合は、つかったお金以上のお金が戻ってくるのか…ということも考えなければなりません。
値段の高い・安いとは別に。
そうでなければ、赤字になり、いずれはお金が足りなくなりますから。
もし、つかったお金以上のお金が戻ってくるのなら、どんなに高いものであっても、事業は成立しているといえます。
「以上」ではなく「超」が望ましいですけれどね。
そのためには、お金をつかって手にいれたモノやサービスに、自分がなにかしら手を加えてから売る。
手を加えた結果を付加価値とよびますが、どれくらいの付加価値かにより、売上として戻ってくるお金は変わってきます。
値段にかかわらず、ここまでを想定してお金をつかうのが、経営者のありかたといえるのです。
もちろん、いつもいつもこんなことを考えていると、息が詰まるかもしれないですね。
趣味とか、試しとか、遊びがあってもよいものです。
ただ、お金自体ではなく、それと引きかえに手に入れるものを基準にする。
その手にいれたものに、自分はどんな付加価値をくわえられるか。
こう考えてみれば、値段には惑わされにくくなるのではないでしょうか。
お金は道具
結局のところ、お金は、それと引きかえに何かを手に入れるための道具です。
ただ、その道具も使いかたにより、いろんな結果を招きます。
たとえば椅子に座ればラクになりますが、その椅子を、重いですが、ブンブン回したりすれば、自分や周りが傷つくこともある。
お金も、使いかたによっては同じことですよね。
たとえば今日の使いかたはどうだったか…振り返ってみましょう。
お金を使うことで、自分は何か変わったのか…などと。
どんな道具も、いきなり上手く使えるようになるものではないです。
練習も必要。
ただ、何をもって上手いというのかは、人それぞれです。
お金は生きている限り必要なものなので、人生まで考えなければならないですから。
と、そこまで深い話にはせずとも、お金は道具ゆえに使いかたで変わることがある…と意識してみましょう。
・