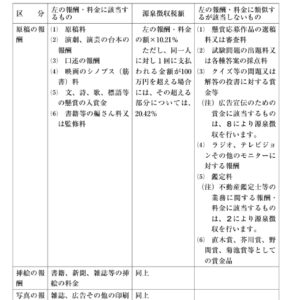寡黙な数字がしゃべるようになるには
数字をみると、それに触発されて出てくる感想があります。
その触発されることが、数字がしゃべるということ。
どうやったら数字がしゃべるのか、みていきましょう。
数字の声
比喩的なお話ですが、数字にも声があります。
たとえば、ダイエットをしているとき。
きっと、定期的に体重をはかりますよね。
そんなときに、「目標まで、あと○㎏だよ」と。
場合によっては、「順調、順調」とか「まだ食べすぎだよ」とか。
誰かと待ち合わせをしているときも、そうですね。
「予定の時刻まで、あと○○分」
「急いだほうがいいよ」とか「すこし寄り道をしても大丈夫」とか。
もちろん、数字自体がしゃべっている訳ではありません。
数字に触発されて、自分のなかに感想がわきおこる。
これが、いわば数字の声なのです。
数字がなかったら、存在しなかった感想…といえますから。
さて、決算書や試算表など、事業における数字からも、声は聞こえるでしょうか。
そのままでも、いくらか声は聞こえるかもしれませんね。
事業をしていれば、だれでも欲しいものや目指すところはあるでしょうから。
それに照らせば、感想がゼロということは少ないはずです。
ただ、決算書などの数字は、基本的には、社外のかたに見せるためにルールが作られています。
専門的には、財務会計と呼んだりするんですけれどね。
こうした数字は、すこし建前のようなところがあります。
感覚的なことなんですが…
たとえば、うえのダイエットのこと。
現状の体重は、決算書にあらわれるとしましょう。
でも、目標としている体重は、決算書にはあらわれない。
もし、それを口にすれば、どう思われるか…と気になりますしね。
待ち合わせの時間にしても、似たところがあります。
本来の時刻は、決算書にあらわれる。
でも、「この相手なら10分前にはいないとマズそう」とか「すこし遅れてもちゃんと謝れば大丈夫」といったことは、決算書にはあらわれない。
つまり、決算書などの数字には、本音があらわれない…という面があるのです。
ゆえに、声が聞こえずらいときがあったりする…と。
数字の声は、本音から出てくるものですから。
では、どうやったら数字の声が聞きやすくなるか、数字がしゃべるようになるか。
どうやったら数字がしゃべるか
決算書の数字が、そのままではしゃべらないときは、次のことを試してみましょう。
- 分ける
- 比べる
- まとめる
分ける
決算書などの数字は、売上や給与など、科目ごとにまとめられています。
そのまとめられた状態のままでは、分からないこともあります。
たとえば、売上。
相手先ごと、自社のスタッフごと、商品やサービスごと、場所ごと、季節ごと、定期的なものと臨時のもの、金額帯…など。
こうしたもので分けると、売上全体としてはよいと感じるときであっても、「○○は良かったけれど、△△は気になる」といった感想が出てくることもあるかもしれません。
また、売上自体も、次のように分けることができます。
- 数 × 単価 × 頻度
このように分けるには、決算書などの会計データ以外から、数字をもってこなければなりません。
でも、分けることにより、さらなる感想がでてくるでしょう。
すると、たんに売上を増やそうとするのではなく…
- ある相手に、売る数を増やせないか
- ある場所では、単価を変えられないか
- ある季節は、来てくれる頻度をあげられないか
このように、変えようとするにも具体的になってきます。
きっと、それぞれ「出来そう」とか「いまはムリ」という声が聞こえるかもしれませんね。
分けるからこそ、数字がしゃべることもあるのです。
比べる
この比べることは、すでに誰でもやっています。
売上と経費を比べたけっかが、利益ですから。
また、自分の希望と比べることも、自然にやっていると思うのです。
でも、もう少し…
利益にしても、いくつか種類があります。
売上から、商品などの原価だけをひいたものが粗利。
そこから、本業のための経費をひいたものが、営業利益。
さらに、経常利益などもあります。
このうち、どこがどうなのか…?
それにより、打てる手は変わってきます。
また、経費にしても、決算書とは別の方法で分けることもできます。
売上の増減と、おなじように増減する経費(変動費)。
売上がゼロでも、固定でかかる経費(固定費)。
この分け方から導きだされるものが、損益分岐点などです。
気になったら「管理会計」と調べてみましょう。
さらに、自分の過去や将来の希望、もしあれば同業他社のデータ。
こうしたものと比べることもできます。
本屋さんでみかける決算書の分析についての本も、おおくは比べることをベースにしています。
この比べるということは、とても多岐にわたり、ときに複雑に感じることもあるはずです。
とはいえ、比べることは、目標や希望があるなら、必須のこと。
シンプルに「これくらいのお金は欲しい」と考えてみましょう。
すべては、そこから始まるのですから。
まとめる
決算書などでは、おおくの数字がならんでいます。
すべてに目を通そうとすると、わずらわしい…と感じたりするでしょうか。
それは、もしかしたら雑音かもしれません。
「ちょっと、うるさいよ。静かにしてくれない…?」と。
そんなときは、気にならないものをまとめてしまいましょう。
「その他の経費」などと。
どんな業種でも、売上と人件費、そして利益は、かならず知っておかなければならない数字です。
それ以外は、商品があるなら売上原価、サービス業なら外注費や手数料あたりが重要になってくるのが一般的。
これらに加えて、自分が気になるものをピックアップし、残りはまとめると、数字が見やすくなるはずです。
また、「1,029,586円」といった数字も、「だいたい100万円」としたほうが、頭に入ってきやすいです。
数字自体も、まとめる…と。
すべての声を聞くことも、それはそれで良いことかもしれません。
いっぽう、それにより、ものごとがハッキリしなくなることもあります。
わずらわしいと感じたら、それは雑音ですから、聞こえないようにまとめましょう。
まとめ
数字の声。
それは、数字に触発されてでてくる自分の感想です。
その感想が、事業の行く末を左右するのではないでしょうか。
なるべく数字の声が聞こえてくるように、分ける・比べる・まとめることを試してみましょう。
決算書などの数字を、そのまま鵜呑みにしていては聞こえない声もあるのですから。
もし、その声が聞こえれば、ちがった結末が待っているかもしれませんよ。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。