年末調整の還付で預り金がマイナスになるときはどうするか
年末調整の還付が多いと、預り金がマイナスになることもあります。
そのときにどうするかを確認しておきましょう。
なお、今回の記事でいう預り金は、すべて所得税です。
なぜ預り金がマイナスになるのか
預り金は、つぎのサイクルで増減を繰り返します。
- 役員報酬や給与から、所得税の天引きをする……増える
- 天引きした所得税を、税務署へ納める……減る
先にあるのは、役員報酬などからの天引きです。
その後に、税務署へ納める。
ですから、天引きした金額をそのまま税務署へ納めれば、預り金の残高はゼロになります。
たとえば、天引きが「100」で、そのまま税務署へ「100」納めるとき。
このとき、天引きにより預り金は「100」増え、納めることで「100」減る。
結果、プラマイゼロと。
こんな風になるわけです。
ところが、預り金が減る要素は、もう一つあります。
それが、年末調整の還付です。
年末調整の還付とは、1月~12月の間に、そのかたの役員報酬などから天引きした所得税の一部を返すこと。
税務署へ納めるときのように、お金が出ていけば預り金は減るのです。
この年末調整の還付は、12月の天引きの一部で済むこともあれば、10月~12月分をまるまる還付するようなこともあり得ます。
生命保険や住宅ローン控除などが、年末調整のときにまとめて出てくる…というのが理由のひとつ。
それとは別に、役員報酬などが激減したときも、12月の天引きにたいして還付は多くなりがちです。
激減する前に、大半の天引きがされていれば、還付もその時期の分までさかのぼる。
こんな可能性があるからです。
それまで会社員だったかたが法人成りをし、1期目はすくない役員報酬にしておく。
こんなケースでは、12月の天引きにたいして還付は多くなります。
すると、天引きは「100」なのに、還付は「300」。
こういうことも起こり得ます。
納期の特例をつかっていても、仕組みはおなじ。
6月~12月の天引きが「100」なのに、還付が「300」ということはあり得るのです。
このとき、天引きにより預り金は「100」増えますが、還付により「300」減る……?
すると、預り金はマイナス値である「△200」になってしまいます。
こんなときにどうするか、確認していきましょう。
なお、預り金は、役員やスタッフ個別にみるのではありません。
役員やスタッフ全員分に、弁護士や税理士への報酬をくわえたものでみます。
預り金がマイナスになるときはどうするか
預り金がマイナスになるときの対処法は、つぎの2つです。
- 年末調整の還付は1月以降にもする
- 年末調整過納額の還付請求をする
年末調整の還付は1月以降にもする
天引きが「100」のときに、「300」を還付する。
このときは、会社や事業主が差額の「200」を立て替えることになります。
とうぜん、そんなお金の余裕はないこともあります。
なので、立て替えることは義務ではありません。
こんなときは、翌年1月以降に天引きするものから、還付していきます。
還付がすべて終わるまで。
このときは、天引きした所得税の納付書の書き方に気を配っておきましょう。
まずは、年末調整をする12月のもの。
天引きが「100」だったら、仮に本来の還付が「300」だったとしても、還付は「100」だったと記載します。
納付書の一番下、合計額は「0」になるようにするのです。
天引きが「100」で、還付が「300」。そして合計が「△200」。
このようにはならない…と知っておきましょう。
国税庁が公表している資料にサンプルがあるので、貼っておきますね。
過納額とは、ほんらい還付すべき金額。
源泉徴収税額とは、天引きした所得税のことです。
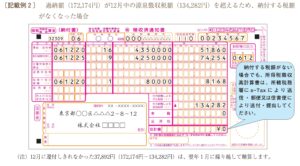
(国税庁「令和6年分 年末調整のしかた」より)
それから1月以降は、還付する金額を「年末調整による超過税額」のところに記載します。

年末調整過納額の還付請求をする
年末調整の還付が、毎月の天引きにたいして大きすぎるようなこともあります。
そんなときは、税務署に、役員やスタッフに還付できなかった分を返してくれ…と請求することができます。
それらは、すでに税務署へ納めているものですから。
これを、年末調整過納額の還付請求といいます。
年末調整過納額とは、ほんらい還付すべき金額のうち、まだ還付できていないもの。
かりに還付したとしたら、預り金がマイナスになる。
そのマイナスの金額をいいます。
ただし、12月の時点ですぐにできる…とは思わない方がよいです。
通常の場合なら、おそらく3月以降になるかも…と。
詳しくは、「年末調整過納額 還付請求」などと検索して、国税庁のHPを調べてみましょう。
「A2-17 源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求」というページに載っています。
その還付請求では、1年分の給与などの内訳を記載する「源泉徴収簿」を添付します。
年末調整をした年の分と、場合によっては翌年のものも。
それぞれに、年末調整過納額の内訳や推移を書くことになる…のを忘れずに。
年末調整をした年は、下のところ。翌年は、上のところ。
それぞれ赤く囲ってあるところです。
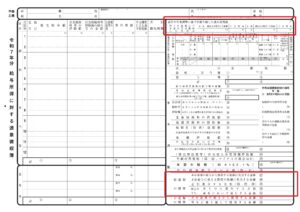
また、転職をしたときは、前職の源泉徴収票を要求される可能性もあります。
電話がくることもあるので、それを避けたい場合は添付しておくのもよいです。
まとめ
年末調整の還付により、所得税の預り金がマイナスになる。
そんなときにどうするかを確認してきました。
年末調整が終わったら、その時点の預り金残高も確認しておくようにしましょう。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。


