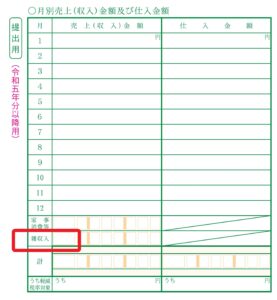現金、預金、事業主勘定の違いと使いかた
現金も預金も、現実ではお金と一括りにするものです。
でも、会計ソフトに入力するときは、ちゃんと区別しなければ正しい貸借対照表を作れません。
青色申告特別控除にも影響するため、その違いと使いかたを確認しておきましょう。
正しく使えなければならないわけ
事業所得や不動産所得があるかたにとって、貸借対照表をつくれるかどうかは税金にも影響します。
貸借対照表がなければ、青色申告特別控除は10万円が限度です。
いっぽう、あるなら、それは55万円または65万円になります。
個人の税金で…
所得税の最低税率は5%です。
そして、住民税の税率は、固定で10%。
あわせて15%なので、もし65万円の控除をとれるなら、少なくとも65万円の15%、つまり「97,500円」も税金が安くなるわけです。
貸借対照表は、とりあえず会計ソフトに入力をすれば、ボタンひとつで作れます。
でも、入力した会計データ(=仕訳)が正しくなければ、貸借対照表も正しいものとはなりません。
とくに多いのが、残高がマイナスになっている間違いです。
残高とは、その時点で持っている金額のこと。
なので、その残高がマイナスになることはあり得ないのです。
(ごく稀、そして専門的なものについて例外はあります)
たとえば現金がマイナスになるということは、誰かから借りているということです。
手持ちの現金はゼロで、借入金がいくらかある…のが正しい状態なのです。
事業をしていれば、現金や預金との付き合いは避けて通れません。
そのため、会計ソフトに入力するときも、これらの科目は使わざるを得ない。
正しい貸借対照表のためにも、お金に関係する科目の違いや使いかたを押さえておきましょう。
ちなみに、税金が還付になるときは、税務署での審査があります。
そのとき、貸借対照表にマイナスの残高になっているものがあれば、その申告書はあきらかに正しくないもの…と捉えられます。
「この申告について、素直に還付するわけにはいかない」と思われてしまうでしょう。
すると、申告をした後で、税務署から「申告内容についてお聞きしたいのですが…」と電話がくるはずです。
…ということを避けるためにも、正しい貸借対照表をつくる必要があります。
現金、預金、事業主勘定の違いと使いかた
現金、預金、事業主勘定の違いと使いかたを確認していきましょう。
現金
現金とは、「事業用」のものを意味します。
財布が、事業用とプライベート用の2つある状態をイメージしてみましょう。
そのとき、事業用の財布にいれるもの、あるいは出てくるものが「現金」です。
プライベート用のものは、現実では現金であっても、会計データでは「事業主勘定」をつかいます。
それが事業用の財布だったとして、簡単な例で仕訳をみておきましょう。
- 売上を現金で受けとった……現金/売上
- 経費を現金で支払った………○○費など/現金
もし、プライベート用の財布なら、仕訳はつぎのように変わります。(現金→事業主勘定)
- 売上を受けとった……事業主貸/売上
- 経費を払った…………○○費など/事業主借
事業主勘定をみるときは、次のように考えるとよいです。
- 事業主貸……事業のお金を、プライベートの自分(事業主)に貸す
- 事業主借……事業のお金を、プライベートの自分(事業主)から借りる
でも、事業主勘定の意味をいつも押さえているのは、難しいかもしれませんね。
わたしも時々、理屈ではどっちがどっちか…考えこんでしまうことがあります。
なので、次のように左右のどちらか…で覚えるほうがラクです。
- 事業主貸(左)……事業主借(右)
結局のところ、事業主勘定の残高は相殺され、元入金に組み込まれます。
たしょう間違ったとしても、翌年は、一緒くたにまとまってしまうのです。
ところで、財布を事業用・プライベート用と2つ持っている方はどれくらいいるのか…?
多分、少数派ではないかと思うのです。
もし、事業・プライベートの区別をしていないのに「現金」をつかうのであれば、それはある意味正しくない…といえます。
プライベートの現金を、事業につかっているかもしれません。
あるいは、その逆も。
なので、「現金」という科目をつかわない…という選択肢もあります。
ぜんぶプライベートの現金にしてしまう…という前提です。
受けとった売上は、すぐにプライベートの財布にいれる。
経費は、いつもプライベートのお金から出している。
こんな解釈の仕方です。
へたに貸借対照表に現金を載せたとしましょう。
でも、現実では、そんな残高にはなっていないこともあるでしょう。
なので、「現金」をつかわない…というほうが正しい状態なのかもしれません。
こうすると、会計ソフトの入力をするとき、きっとラクになります。
考える時間が、すこし減りますから。
「現金」をつかわない…という選択肢も検討してみましょう。
預金
預金は、貸借対照表に載せる口座を意味します。
貸借対照表に載せない口座は、事業主勘定で入力するのです。
もちろん、貸借対照表に載せるのは、事業でつかっているものであることは当然です。
ただ、事業でつかっていたとしても、あまり動きがないようなものは、載せない…という選択肢もあります。
(口座名義が屋号になっているものは、かならず載せましょう)
持っている口座を、すべて載せなくてはいけない…わけではないのです。
貸借対照表に載せる口座は、すべての入出金を入力します。
いっぽう載せないものは、事業のものだけを、「預金」ではなく「事業主勘定」をつかって入力します。
もしかしたら、預金も現金とおなじく、すべて事業主勘定で入力する…ということを考えるかもしれません。
でも、これは止めておきましょう。
よほどの事情がない限り、預金口座は持っているものです。
そして、残高をチェックするのも、現金にくらべれば段違いにラクです。
1月1日と12月31日の数字を見るだけでよいので。
貸借対照表に預金がないのは、かえって不自然だと思いましょう。
入力が終わったら
貸借対照表に載っている科目の残高は、正しくなければなりません。
というのも、来年は、その残高からスタートするからです。
もし残高が間違っているのなら、その間違いを引きずりつづけることになってしまいます。
すると、いつか間違いに気づいたとき、それを直すのが大変なこともあります。
過去○年分の申告をやり直す…など。
なので、入力が終わったら、かならず残高が合っているかの確認をしましょう。
預金は、通帳を見るだけでチェックできます。
その他の科目は、「何が・誰に対して・いくらあるか」が分かるようにしておきましょう。
もし残高が合っていなければ、もしかしたら収入や経費・利益が違うかもしれません。
複式簿記では、間違いが1つあると、かならず他で1つ以上の間違いがあるのです。
これは、複式簿記の特性・素晴らしいところでもあるんですけどね。
会計ソフトの入力が終わったら、かならず残高のチェックをするようにしましょう。
まとめ
現金、預金、事業主勘定の違いや使いかたについて確認してきました。
現実では、どれもお金と一括りにするものです。
でも、会計ソフトの入力をするときは、結構気をつかうもの。
とくに、間違いを数年にわたって引きずり続けないように、注意しましょう。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。