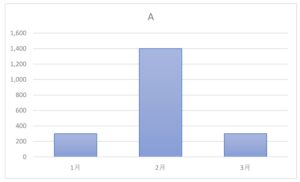将棋の評価値を気にするか
将棋を観ているとき、評価値があると想像が広がります。
事業においても、評価値があっていいんじゃないか…と。
評価値があるから分かる
将棋を観戦していると、評価値やつぎの候補手も表示されます。
その評価値とは、AIによる形勢判断が数値であらわされたもの。
きっとAIが、○通り○億手など、とんでもない数の指し手を読み、その結果でてきた数値だろうと思われます。
ただし、戦っている棋士には見えません。
つぎの一手をどうするかには、形勢をどう判断するかも材料になるわけで。
それも含めて、つぎの一手を考えるべきでしょうから。
もし優勢なら、安全策をとるかもしれません。
逆なら、ふつうは指さないような手を選ぶかもしれません。
こうした材料は、自分自身で集めるのも将棋の一部ですしね。
でも素人には、評価値があると楽しみが増えます。
盤面をパッと見たところで、形勢なんか分かるものではないです。
プロの将棋では、明らかに詰んでいる状態まで指さないことも多いですし。
それでも評価値をみれば、答えを知りつつ、今どうなっているか…を考えることができます。
考えるというより、なんとなくの想像にすぎないですけどね。
飛車と角の両方を相手に取られていたり、王将の周りがスカスカでも、形勢はよいこともあります。
先に相手の王将を詰ませればよいので、自分の状況なんかどうなっていても構わないようなときもあり得るわけです。
評価値があることで、実力はないものの、その実力があるひとの立場にたてたような気になる。
すると、「なんでこんなに考えているんだろう」といったことにも、推測の幅が広がります。
自分には持てない視点を垣間見ることができるので、評価値があると楽しみが増えるのです。
ところで、事業における評価値も気にしているでしょうか。
評価値を気にするか
事業における評価値は、決算書や試算表などからも計算することができます。
でも、これら単体では評価値を計算できません。
将棋における勝ちにあたるものや、相手が考慮されていないからです。
「○○したいけど、今は△△になっている」
決算書などから分かるのは、「今は△△になっている」ことだけです。
「○○したいけど…」が分からないと、評価値は計算できないのです。
評価値とは、「○○したいけど…」に照らして優勢なのか劣勢なのか…ということですから。
「○○したいけど…」は、将棋における勝ちに相当するものなのです。
また、「○○したいけど、××だから、今は△△になっている」ということもあるでしょう。
この「××だから…」は、相手に相当するものといえます。
勝ちたいけど、相手もなかなかやるから、今こうなっている。
ここから導きだされるものが、評価値です。
なので、事業における評価値を計算するのは、とても難しくなります。
計算の要素は数字だけではないですし、数字にあらわせないものをどう捉えるか…という問題もあるので。
それでも、評価値はどうなっているか…は気にしてみましょう。
将棋の勝ちにあたるものは、そう難しくないはずです。
それは、「どうしてその事業を始めたのか」ですから。
始めた結果、今どうなっているか…が気にならない人はいないと思うのです。
そして、その結果、とりあえずの結果が、決算書や試算表です。
もしかしたら、「どうしてその事業を始めたのか」を数字に置きかえるのは難しいかもしれません。
そんなときは、事業が上手くいったときのお客さまや商品・サービス内容を想像してみましょう。
実現する可能性が低くてもよいのです。
それでも、とりあえずの数字を出してみる。
もし、とんでもなく現状と開きがあるなら、段階をふんで達成することも考えてみましょう。
その段階の一つを、勝ちとすればよいですから。
そうすれば、「できるかも」と思えるはずです。
せっかく事業を始めたのなら、評価値も気にしてみましょう。
かならずしも数字である必要はないです。
良さそう・悪そう…でもよいのです。
ただ、気にすることにより、今どうするか…が変わる可能性があります。
事業をしていれば、「○○しなければならない」場面も増えてくるはずです。
でも評価値を気にすれば、「○○したいけど」を思い出すはめになります。
そして勝ち、つまり将来を意識することにより「○○すべきだ」という感覚も増えてくるでしょう。
事業にかぎらないですが、「しなければならない」よりも「したい」「すべきだ」を増やすのがよいと思うのです。
評価値が、そのきっかけになれば。。。
まとめ
「○○したいけど、××だから、今は△△になっている」から導きだされるものが評価値です。
それが上手くいっているか・いっていないか…をあらわすものとして。
とくに「どうしてその事業を始めたのか」は、折にふれて思い出せるようにしておきましょう。
変わってもよいのですが、ゴールがないのは問題ですから。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。