年収の壁は令和7年(2025年)からどう変わったか
年収の壁は、とてもややこしいものです。
令和7年(2025年)から改正されたので、いちど整理しておきましょう。
年収の壁とは
年収の壁とは、それを境に、税金や社会保険がかかる金額をいいます。
そこまでの金額だったら、税金または社会保険もかからない。
その金額を、年収の壁とよんでいます。
ややこしいのは、税金が2つ(所得税と住民税)、そして社会保険(健康保険と年金)。
これらの年収の壁が、それぞれ別だということ。
所得税
所得税における年収の壁は、これまで「103万円」でした。
年収がこの金額までなら、「所得税はゼロ」だったのです。
なお、この年収は給与や役員報酬だけ…という前提です。
業務委託や不動産収入など「給与所得」にならない収入があると、年収の壁も変わります。
経費が変わるので。
なので、今回は収入が「給与所得になるものだけ」という前提で話をすすめます。
まずは、どんな理屈で「103万円」が年収の壁といわれたのか。
その仕組みを確認しておきましょう。
所得税は、1月~12月の収入にたいしてかかります。
その年収からは、経費(給与所得控除)と、医療費などの所得控除をひきます。
その残り(課税される所得)に税率をかけ、所得税が計算されます。
これを図にすると、つぎのとおり。
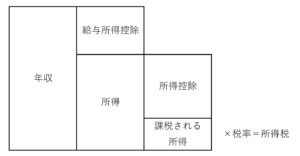
うえの給与所得控除、そして所得控除のひとつである「基礎控除」には、それぞれ次の最低保障がもうけられています。
- 給与所得控除……55万円
- 基礎控除……48万円
この最低保障だけを合算すると、「103万円」。
課税される所得はゼロになるので、所得税もゼロになるのです。

住民税
住民税の計算は、所得税とほとんど同じです。
ただ、基礎控除は違います。
住民税の基礎控除は、「43万円」だったのです。

すると、住民税がゼロになる年収の壁は、所得税とは違うものになる。
もし、最低保障だけで考えるなら、つぎのとおり98万円です。
- 給与所得控除……55万円
- 基礎控除……43万円
- 合 計……98万円
ただ、住民税には「均等割」とよばれる部分があります。
自治体により金額が変わりますが、だいたいが5,000円前後。
これは、その自治体に住んでいるなら、だれでも固定でかかるもの。
住民税は、収入にかかる部分と均等割。
この2つから成っているのです。
すると、最低保障だけでかんがえた年収であっても、厳密には住民税がゼロにはならない。
そこで、均等割もゼロになる、つまり住民税が完全にゼロになるラインがもうけられています。
その金額は、年収「100万円」。
(この金額は自治体により変わる可能性があります)
この金額を、非課税限度額とよびます。
お住まいの自治体ごとに検索などして調べてみましょう。
社会保険
社会保険における年収の壁とは、家族の扶養になれるかどうか。
これをあらわす金額のことをいいます。
よく言われるのは「106万円」と「130万円」の2つの年収の壁。
このうち「106万円」は、従業員51人以上の企業などで、週20時間以上勤務しているときのこと。
そのときに年収が「106万円」を超えると、単独で社会保険に加入することになるのです。
いっぽうの「130万円」は、家族が加入している社会保険により変わる可能性があります。
それぞれの団体で確認しておきましょう。
2025年からどう変わったか
年収の壁は、税制改正により、つぎのように変わりました。
- 所得税……160万円
- 住民税……110万円
それぞれの内容と、扶養についても確認しましょう。
所得税
つぎの2つの合わせ技により、年収の壁は「160万円」に引き上げられました。
- 給与所得控除……最低保障が、55万円から「65万円」になった
- 基礎控除……年収160万円なら、48万円から「95万円」になった
つぎのとおり、年収160万円までなら所得税はゼロになるのです。

でも、年収160万円だと、住民税はかかってしまいます。
住民税
住民税でも改正がおこなわれましたが、所得税とおなじではありません。
- 給与所得控除……所得税とおなじように改正された
- 基礎控除……改正はされていない
これにより非課税限度額は、100万円だったものが「110万円」になりました。
でも、所得税にあわせて、もし年収が160万円になるなら、住民税と社会保険はつぎのとおり。
- 社会保険の扶養になれる……住民税は約6万円(手取りは約154万円)
- 社会保険の扶養から外れる……住民税は約3万円、社会保険は約24万円(手取りは約133万円)
だいぶ混み入ってきましたが、税金における扶養のことも考えておきましょう。
扶養のこと
税金における扶養とは、配偶者控除・扶養控除のことをいいます。
どちらも基本の金額は38万円で、つぎのとおり所得控除にふくまれるものです。
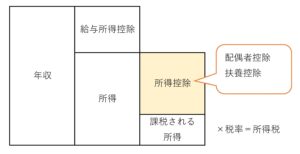
これらの控除をとる、つまり税金における扶養になるための条件は、つぎのとおりです。
- 配偶者や扶養親族の所得が「58万円以下」であること
これを年収におきかえると「123万円」です。
ここまで、改正後の年収について、つぎの数字がでてきました。
- 所得税……160万円
- 住民税……110万円
- 税金における扶養……123万円
これにくわえて社会保険の「106万円」「130万円」も。
さらに、19才~23才未満の扶養親族については、年収が188万円以下であれば、いくらかの扶養控除をうけられる。
じつは、こんな改正もおこなわれました。
税金と社会保険をふくめたところでの最適解は、とても一言ではあらわせない。
それくらい、ややこしくなっています。
どうするのが良いのか…?
これは、家族全体の収入や働きかた・家族構成。
これらをベースにした今、そして将来の見通しによっても変わります。
それを踏まえて…
もし自分で立ち上げた会社を経営しているなら、自分の年収はこだわらなくてもよいのかもしれません。
ひょっとしたら、会社の利益との兼ね合いはあるかも。
あるいは、いわゆるマイクロ法人なら、今まで通りかもしれません。
もし扶養されている側なら、意識すべきはむしろ社会保険でしょうか。
金額だけみれば、税金より社会保険の方が大きいですから。
将来の年金のことがありますけれどね。
今回の改正は、たしかに減税です。
でも、税金よりも金額がおおきい社会保険は、今まで通り。
適用対象が拡大されるという噂は聞きますが、まだ確定ではないようです。
税金だけではなく、社会保険料もあわせて考えるようにしておきましょう。
まとめ
令和7年(2025年)からの年収の壁について、みてきました。
年収の壁は、所得税、住民税、社会保険それぞれ違います。
家族で会社を経営している場合は、いちど整理をしておきましょう。
12月の年末調整のときに「あれ?」とならないように。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。


