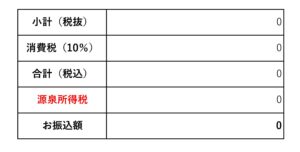経営者の仕事は付加価値をつくること
付加価値は、粗利として会計データにあらわれます。
その付加価値の意味や向き合いかたについて、確認しておきましょう。
付加価値とは
付加価値とは、「粗利」のことです。
(付加価値については、いろんな解釈のしかたがありますが、ざっくり大筋でみていきましょう)
その粗利とは、売上から、売上に直接ひもづく経費だけをひいたもの。
この経費を、「変動費」とよぶこともあります。
たとえば、商品の仕入れが、それにあたります。
変動費は、売上に比例して、増減するもの。
その変動費以外の経費を、「固定費」といいます。
固定費は、売上がゼロでもかかるもの。
家賃や固定でかかる人件費などが、それにあたります。
ここまでをまとめると、つぎのようになります。
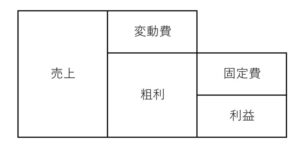
たとえば、「100」で仕入れたものを、「150」で売る…
このときの粗利は、「50」です。
この「50」が意味するところが、付加価値です。
たとえば、スーパーやコンビニにおいてある食べ物をかんがえてみましょう。
そのときの付加価値には、つぎのような意味がありそうです。
- わざわざ、農家や漁港などに買いにいかなくてもすむ
- 料理の手間をはぶくため、切り身になっていた
- 清潔そう
- 変なものは、売ってなさそう
- 毎日、いつでも買うことができる
- 必要なぶんだけ、買うことができる
- 料理のレシピも置いてある
- 包装してあるので、手がベタベタにならない
きっと、他にもたくさんのことがあるでしょう。
それらが、付加価値として、粗利である「50」に詰まっているわけです。
この付加価値は、きっと、たくさん頭をひねったすえ、でてきたアイディアによるもの。
もちろん、苦労も。
そうしたことを経て、スーパーやコンビニが作り出したものです。
それがあるから、「100」で仕入れたものが、「150」で売れるわけです。
ここまでが、付加価値の意味です。
経営者の仕事
さきほどの図を、もういちど見てみましょう。
こんどは、固定費と粗利のかんけいを。
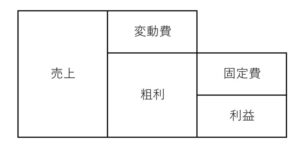
固定費は、売上がゼロでもかかるもの。
そして、事業をつづけていくかぎり、必ずかかっていきます。
なので、つねに、固定費以上の粗利が必要なのです。
売上ではなく。
売上がどんなに多くても、粗利が固定費をカバーできないのなら、赤字になってしまいます。
また、売上は、業種や付加価値によっても変わるもの。
たとえば、小売業とサービス業では、「%」でみた粗利は全然かわりますから。
とうぜん、業種の垣根をこえて、売上をきそいあっても意味はない…
売上が大事じゃない…とはいいませんが、それ以上に粗利が大事だとおもいましょう。
なので、経営者は、必要な粗利がどれくらいなのか…は、いつもチェックする必要があります。
もし、付加価値をあげることができるなら、粗利も稼ぎやすくなります。
このことを考えるのも、もちろん経営者の仕事です。
ですが、これはとてもむずかしいこと…
たとえば、高級料理や高品質サービス。
なんか、付加価値がおおきそうなイメージではないでしょうか。
値段も、きっと高いでしょうから。
でも、実情はちがっているかもしれません。
というのも、変動費などの経費もふえているかもしれないので。
すると、粗利にしてみると、そこまで…ということも。
目指すべきは、粗利であり、付加価値です。
その付加価値は、お客さま次第でもあります。
- 欲しいものが買えた
- きもちいい買い物ができた
- 悩みが解決できた
- 来てよかった・嬉しかった・楽しかった・安心した
商品やサービスを介して、あいての感情にうったえる…ようなことが必要になってくるのです。
付加価値をあげるためには。
(もちろん、ほかの方法もあろうかと思いますが…)
もちろん、値段には相場もあります。
これがおおきな障害になることもありますが、付加価値をあげることをかんがえてみましょう。
すると、稼ぎやすくなり、お金や時間の余裕もうまれます。
そのうまれたお金や時間をつかい、さらなる付加価値のアップへ…
と、好循環ができていきますから。
きっと、仕事の楽しさも変わっていくはずです。
まとめ
付加価値の意味、付加価値を考えたり・あげていくことの意義について、みてきました。
仕事とは、付加価値をつくること…ともいえます。
その仕事を表現するときに、「こなす」とか「作業する」ということもあります。
でも、付加価値をあげることに目を向けると、こうした表現にはならないはずです。
すると、楽しい・嬉しいとおもえる場面もふえてくるかも…。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。