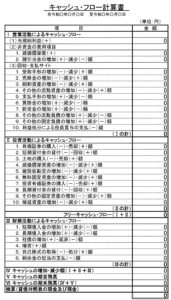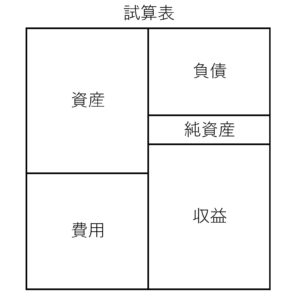法人成りした時に気をつけたい役員報酬のこと
法人成りしたら、生活費は役員報酬でまかないます。
その役員報酬について気をつけるべきことを確認しておきましょう。
法人成りをした後の生活費はどうするか
法人成りをすると、事業は会社のものとなります。
だから売上や経費はもちろん、それにまつわるお金も会社のもの。
すると出てくるのは、社長自身の生活はどうするのか…という疑問。
それは、会社から役員報酬をとることで、まかなっていきます。
経費には、あらたに役員報酬が加わることになるのです。
この役員報酬には、法人税において厳しめのルールがあります。
また、事業のお金は会社のものであり、社長個人のものではない…という不自由さ。
これらを踏まえて、役員報酬について気をつけるべきことを確認しておきましょう。
役員報酬について気をつけるべきこと
役員報酬をめぐっては、次のことに気をつけましょう。
- 法人税等におけるルール
- 会社と個人の税金
- お金の貸し借り
法人税等におけるルール
会社の利益には、法人税・住民税・事業税の3つの税金がかかります。
これらの税金に共通して、役員報酬のルールが設けられています。
それは、「毎月の役員報酬はおなじ金額でないと、経費とはあつかわない」というもの。
このルールを満たさない役員報酬は、経費とはカウントせずに利益を計算します。
そして、それにあわせて法人税等もかかることになる。
ただし、経費とはカウントしないからといって、渡したお金を返せ…とはなりません。
気をつけたいのは、お金が減ったのに利益が減らないこと。
すると、手持ちのお金にたいして、割高な税金がかかるようなことになる。
会社のお金をかんがえたとき、これがキツイのです。
もし、このルールがないなら、毎月の利益をそっくり役員報酬におきかえることもできます。
すると、うえの税金もかぎりなくゼロに近づけることが可能になる。
そんな利益調整を防止するために設けられているルールなのです。
ただ、変えて良いタイミングもあります。
それがないと、会社を設立してからたたむまで、ずっと同じ金額が続くことになってしまいますから。
そのタイミングは、原則として「年度が始まってから3か月以内」です。
だから、法人成りをしたら、設立から3か月以内に役員報酬を決めることに気をつけましょう。
また、誤解をまねかないために、支給も3か月以内に始めるのが望ましいです。
この役員報酬をどう決めるか…?
それは、将来の見通しをかんがえ、会社のあり方をふまえて決めるのが理想です。
会社を大きくしたいなら、会社に利益やお金が残るように。
会社がたんに仕事の窓口でよいなら、個人の財布になるべくお金をうつせるように。
また、つぎの税金のことも考えてみましょう。
会社と個人の税金
法人成りをするということは、それまで個人の利益だったものを、会社と個人で分けるようなもの。
すると、つぎのとおり税金の数は増えます。
- 役員報酬(個人の税金)……所得税・住民税
- 会社の利益(会社の税金)……法人税・住民税・事業税
ただし、数が増えたからといって、税金の総額が増える…とは限りません。
その理由は、おおむねつぎの2つ。
- 役員報酬からも経費がひける……給与所得控除
- 所得税は、所得がふえると税率もあがる
給与所得控除とは、役員報酬についての経費のこと。
役員報酬にかかる税金は、年収にかかるのではありません。
まず年収から、その年収におうじて自動的にきまる給与所得控除という経費をひきます。
(自動的に決まるので、領収書のいらない経費のようなものといえます)
それで残ったものから社会保険や扶養の控除などをひき、それに税率をかける。
だから、法人成りをして役員報酬をだすと、給与所得控除という経費が手に入る…と考えましょう。
これも節税のタネなのです。
また、個人事業主のときを思い出してほしいのですが。
所得税は、所得(儲け)が増えると税率もあがります。
ただ、所得すべてにたいして税率があがるのではありません。
○○円までは△△%、それを超えて◇◇円までは××%…というあがりかた。
なので、税率の高いところを役員報酬にすると、トータルの税金は減ることになる。
そんなイメージを持っておきましょう。
なお、会社の税率は、法人税等の合算で、利益の30%前後です。
これと、役員報酬にかかる税率をあわせて考えてみる。
税金のことだけでも、複雑に思えるかもしれませんね。
ただ、お金を会社と個人にどう残していくかも大事なことです。
つぎのお金のことも、忘れずに考えてみましょう。
お金の貸し借り
法人成りをすると、それ以降に事業でふえたお金は、すべて会社のものとなります。
個人のお金は、役員報酬の分だけになるのです。
ただ実際は、会社がピンチのとき、社長が個人のお金をだすこともあります。
また個人のカードで、会社の経費を払うこともあるでしょう。
いっぽう、個人の財布にお金がないときに、会社のお金をつかうこともあったり。
社長の肌感覚では、会社と個人の財布はおなじもの…となっているかもしれませんね。
ですが、これらはすべて、会社と個人のあいだの貸し借りとなります。
それを順調に精算しておけばよいのですが…
会社の利益におうじて、どちらか一方にかたよることも、ときにあります。
利益が大きければ、個人が借りる傾向がある。
いっぽう利益が少なければ、会社が借りる傾向があります。
そんなとき、会社から個人に貸しているお金が多額になることも。
つまり、役員報酬だけでは、個人の生活が足りないときですね。
もし、その状態を放置していると。
会社から個人に貸したぶんは、役員へのボーナスだとみなされてしまうこともあります。
借りっぱなしで、会社にお金を返す意思がないと思われてしまうときは。
そんなときのボーナスは、ルールから外れた役員報酬として、経費にはならないのです。
こうしたリスクを回避するためには、借りたら返す…をしていかなければなりません。
もし、会社がお金を借りたなら、役員報酬をへらせば、返すためのお金が会社に残る。
いっぽう個人がお金を借りたなら、役員報酬を多めにする。
こんな調整も、必要になってくる可能性があるのです。
くれぐれも、役員報酬は「なんとなく」決めるものではないことに気をつけましょう。
まとめ
法人成りをすると、社長の生活費は役員報酬でまかなっていくことになります。
なお、その役員報酬の15%くらいの社会保険料を、会社が払っていくことも知っておきましょう。
それまでの国民健康保険・国民年金は、会社を経由して、協会けんぽなどの健康保険と厚生年金に切り替わることになるのです。
このことと、法人税等のルール、節税、お金のこと。
これらを合わせて役員報酬を決めるのが理想です。
役員報酬は、基本的には1年間おなじ金額がつづくもの。
1年あれば、いろんなことが積み重なります。
かりに最初から上手く決められないとしても。
大事なのは、分かったうえで、前もって決めることではないでしょうか。
難しいとしても、あがけば知識やノウハウなどが手に入るはずですよ
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。