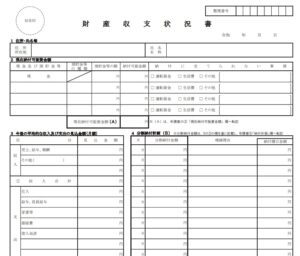会社の赤字のなかでも避けたい3つのパターン
赤字になれば、法人税等もすくなくなります。
でも、その赤字のなかにも気を付けるべきものがあるのです。
赤字のメリット・デメリット
会社を経営しているなら、基本的に、赤字は避けるべきものです。
もちろん、避けようとしても避けられない…という難しさはありますけれどね。
ただ、赤字になれば、つぎのようなデメリットがあるのです。
- 会社のお金がへる
- 融資が受けづらくなる
- 入札や取引先の審査が通りにくくなる
いっぽう、赤字にはつぎのようなメリットもあります。
- 法人税等がすくなくなる
- 赤字の繰り越し控除により、将来の法人税等をへらすことができる
- 個人の財布によりお金をうつしやすくなる
もし上場している会社のように、他人が株主などにいるなら、赤字は出してはいけないレベルのもの。
場合によっては、社長や役員から降ろされてしまいますから。
でも、一人社長や家族経営の会社など、いわゆる同族会社の場合、そういうことにはなりません。
経営者と株主がおなじひとですから、誰も異を唱えることにはならないので。
- 会社は、かならずしも大きくしなくてもよい
- 会社は仕事を受けつける窓口として存在し、お金はすべて個人の財布にながしたい
- 融資などの審査を受けるつもりはない
このような条件があるときは、赤字にしても、そう問題はなかったりもするのです。
いざとなれば、社長や役員個人がお金をだせばよいわけですから。
こんなときは、赤字のメリットである「法人税等がすくなくなること」に魅力をかんじるもの。
でも、そんな赤字のなかでも避けたほうがよいパターンがあることを知っておきましょう。
赤字のなかでも避けたい3つのパターン
同族会社における赤字のなかでも、つぎのようなパターンは避けるようにしましょう。
- 多すぎる役員報酬が原因の赤字
- 粗利や営業利益が赤字
- 赤字の繰り越し控除をしきれない
多すぎる役員報酬が原因の赤字
会社が赤字になれば、住民税の均等割をのぞき、法人税等はゼロになります。
その住民税の均等割とは、赤字でもかかる税金で、最低でも年7万円はかかるもの。
このとき、赤字の原因が多すぎる役員報酬なら、もったいないことになっているかもしれません。
個人の税金や社会保険が、高すぎる…と。
法人税等とは会社の税金で、法人税・住民税・事業税をあわせたもの。
これら3つで、だいたい利益の20~30%くらいです。
いっぽう個人の税金は、所得税と住民税。
計算のこまかいところは省きますが、税率だけをみれば、住民税は10%で固定。
所得税は、5%~45%です。
2つの税率をあわせれば、15%~55%ですね。
もし、その個人の税率が、会社の税率をこえるなら…
会社・個人をトータルでみたときの税金をおさえるため、役員報酬はへらしておいても良かったのかもしれません。
とはいえ、役員報酬の設定はむずかしいもの。
変更できるのは、基本的に年度がはじまってから3か月以内ですからね。
くわえて、仕事に見合った金額でないと、不相当に高額な部分は損金にはならない…という縛りもありますから。
もし、そんな赤字を失敗ととらえるなら、役員報酬を決めるときには先の見通しを考えるようにしましょう。
もちろん、先をかんがえたからといって、その通りになるとは限らないんですけれどね。
ただ、無抵抗のままでいるのと抵抗しようとするのでは、あとあと数字を見る目に差がでてきます。
おそらく、会社・個人をあわせたお金で事業がまわるなら、赤字の痛みを感じにくいはずです。
個人の税金は、まいつきの役員報酬から12分割されて天引きされるので。
一括でまとめ払いするときにくらべ、意識がうすくなるのです。
だから、そもそも多すぎるかどうか…が曖昧になりがち。
あらためて、会社・個人それぞれの税率を確認するようにしましょう。
粗利や営業利益が赤字
会社の利益には、いくつか種類があります。
損益計算書をみてみると、利益と名のつくものが5つあるはずですよ。
その一番うえにあるものが、粗利(売上総利益)です。
粗利とは、売上から、商品の仕入れのように売上に直接ひもづくものだけをひいた利益。
たとえば、「80」で仕入れた商品が「100」で売れたのなら、粗利は「20」です。
この粗利がすでに赤字になっているケースは稀です。
かりに赤字になっているのなら、それは原価割れ。
どうしても売れないものをお金にかえるため、あえて売るようなケースでなければ、異常事態です。
そして、粗利のつぎにくるのが営業利益。
これは、粗利から販売費および一般管理費(りゃくして販管費)をひいたものです。
その販管費は、いわゆる本業にかかわる経費のこと。
役員報酬をはじめ、ほとんどすべての経費が、この販管費にふくまれるはずです。
この営業利益が赤字のときは、もし役員報酬がゼロだったら…として計算しなおしてみましょう。
そこで黒字になるなら、表面上は赤字でも、実質的には黒字といえるわけです。
いざとなれば、社長や役員個人がお金をだす…という前提なら。
だから、いったんは役員報酬がゼロとして営業利益をみたあと、もし生活費が足りるだけの役員報酬をとったらどうなるか…という確認も必要ですね。
ここまでを振り返ると…
もし、粗利が赤字になっているなら、それは異常事態。
それを売れば売るほど、赤字はふえていくわけですから。
そして営業利益が赤字なら、役員報酬をいじって利益を見直してみましょう。
そこで、生活費をまかなえる役員報酬がとれないようなら、事業の見直しも必要です。
これら2つの赤字は重要ですから、気にしてみてくださいね。
赤字の繰り越し控除をしきれない
赤字の繰り越し控除とは、今期の赤字が、将来の法人税等をへらすしくみのこと。
たとえば、今期が「△100」の赤字だったとしましょう。
そして、翌期が「100」の黒字だったと。
このとき、翌期の法人税等をどう計算するか…?
「100」の黒字から、今期の赤字「△100」をひくので、残りはゼロ。
翌期は、黒字なのに法人税等がゼロ…ということになるわけです。
このしくみを、欠損金の繰越控除とよんでいます。
繰越は、今期の赤字を、将来の黒字からひくことができる状態にすること。
そして控除は、じっさいに将来の黒字からひくこと。
かりに繰り越した赤字が「△200」で、翌期が「50」の黒字なら。
「△200」のうち「50」だけを控除して、のこり「△150」はさらに将来へ繰り越されます。
ただ、繰越控除は永遠にできるわけではなく、10年しか繰り越すことはできません。
もし10年たっても控除しきれなければ、その赤字は切り捨てられます。
もはや将来の法人税等をへらすこともできない…と。
そうなると、どうなるか。
そのときは、繰り越し控除できる場合にくらべ、より多くのお金が必要になります。
法人税等をはらうためだけに。
これを、もったいない…と感じるんですね、わたしは。
だから、赤字の繰り越しがあるなら、その赤字を控除できるように黒字にする。
その際には、黒字化のため役員報酬をさげることもあるかもしれない。
すると、個人の税金もへらすことにつながる。
(厚生年金がへると、将来の年金への影響はありますけれどね)
ときには、あえて黒字にするのがよい場面もあることを知っておきましょう。
まとめ
会社、とくに同族会社の赤字のなかでも、避けたほうがよいパターンを確認してきました。
自分や家族で経営していると、他人の目がはいるときよりも、やっぱり甘くなりがちなこともあったりします。
法人税等がすくないことの代わりに、目が曇ることもあるのです。
それを避けるには、「実質的な利益がいくらか」をかんがえてみるようにしましょう。
もし、役員報酬がゼロなら、あるいは○○円なら…と。
数字を見る目は、黒字にしようとするから磨かれる面もあったりしますよ。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。