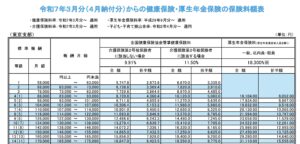偽善から得られるもの。敢えてする理由
傍からみたときに偽善と思われても、迷惑にならない範囲で、敢えてする。
これが、もしかしたら自分の気持ちをコントロールする手段として活用できるかも。
偽善から得られるもの
自分としては良かれと思ってやったみた。
だけど、傍からみれば偽善のように見えることってありますよね。
たとえば…
- 強風で倒れていただれかの自転車を立てなおした
- 自分の経験から「それをするとマズいかも」ということを伝えた
- 電車やバスで席をゆずった
きっと、数え上げればキリがないほど、こうした例はあるとおもいます。
そして、こうした偽善をする動機にもいろんなことがあるはずです。
その動機はともかく、ひとつ言えるのは、偽善をするからには心の余裕が必要だということ。
普通かどうかは分からないんですが…
ふだん過ごしている時間のほとんどは、自分のことで一杯いっぱいだったりしないでしょうか。
自分のことじゃないにしても、やらなければいけないことがあったり…と。
とても、ほかの人のことを考えている余裕はないものです。
その心の余裕は、たとえば自分にとって良いことがあると、生まれたりします。
お裾分けをしたいな…っていう気分になることってないでしょうか。
ギャンブルで勝ったから、おごるよ…でもよいですし。
偽善というのは、相手にとって良いことかどうかは、分からないものです。
- よけいなお世話
- ありがた迷惑
- 押しつけがましい
こんな結果になることもありますからね。
でも、その偽善をしたときの自分の心持ちは…といえば。
余裕もあって、気分もどちらかと言えばよく、やった後も良いことをした気になる。
自分にとっては良い状態のはずです。
偽善は自己満足かもしれませんが、自分にとって良い空気をもたらすわけです。
ここで、偽善とは逆のこともかんがえてみましょう。
偽善の逆は
偽善とは逆に、だれかにイヤなことを言われたり、されたりすると。
しばらくはイヤな気分が続くものではないでしょうか。
どれくらい残るかは、それが何だったかにより違うでしょうけれどね。
ただ、しばらくは全てが上手くいっていないような気にもなるものです。
こちらに非があるなら「まあ、それも分かるけど…」とは思いつつも、気分はスッと晴れないもの。
もし非を感じていないなら、たとえその前が良い気分だったとしても、あっという間にイライラ状態になってしまいます。
気持ちを切り替えるとか、寝たら忘れるとか。
よく言われることですが、実際やろうとすると、なかなか上手くいかないもの。
そして、なぜ相手は自分にとってイヤなことをしてきたのか…とかんがえたとき。
もしかしたら相手もイヤな気分だったのかもしれないですね。
だから、ついつい…ということはありがちです。
つまり、イヤな気分がひとの間を循環する…と。
気持ちとしては分かるんですが、イヤな気分に時間をもっていかれるのは、もったいないものです。
この対策に、偽善をすることは考えられないでしょうか。
あえて偽善をする理由
偽善をすれば、すくなくとも自分の気持ちはよい状態になるはずです。
このよい状態でいることが、けっこう大事なことなんではないか…と。
きっと前向きでしょうし、やる気も自然にでるはずで。
イヤな気分だったりイライラしていると、ミスもしがちだし、はかどり具合もイマイチですしね。
だから、イライラしているなと感じたら、あえて偽善をしてみる。
イライラしているときは自分のことで一杯で、普通はそんなこと考えないと思うんです。
そこを、あえて。
余計なお世話とかにならないように配慮しつつ。
もちろん、気持ちの切り替えがうまいなら、わざわざすることではないんですけれどね。
ただ、自分の気持ちをコントロールするのは、とても難しいことです。
プロのスポーツ選手だって、そのためにいろいろ試行錯誤していますしね。
とくに一人でプレーするゴルフやテニスなどでは、コーチまでつけて。
黙っていても、イヤなこと、上手くいかないことは山ほどやってくるものです。
とくに事業をしていれば、実感できることではないでしょうか。
そんなとき、自分の気持ちを良い方向へもっていくために、偽善だって活用できるかもしれません。
情けは人の為ならずとか、一日一善という言葉があらわすように、古くから人の本質は変わらないんでしょうね。
情報やモノ・環境が変わったとはいえ。
ただ、事業はやっぱり人がいなければ成り立たないもの。
人、つまり人の気持ちや本質とうまく付き合っていくのが、事業の秘訣かもしれないですね。
そこで、偽善が役に立つ余地はないか…かんがえてみましょう。
・