会社の利益がどこへいったのか調べる方法
利益のぶん、お金がふえるとは限りません。
いろんなところに利益はいきますが、どこへいったか調べるには貸借対照表が必要です。
その調べかたを説明します。
利益の4つの行き先
利益がでても、それがそっくりそのまま会社に残るわけではありません。
つぎの4つの行き先に、振りわけられるのです。
- 税金
- 配当金
- 内部留保
- (参考)借入金の元本返済
税金
利益からは、まず税金がひかれます。
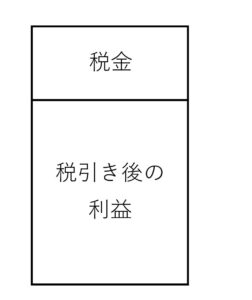
このときの税金は、法人税・住民税・事業税の3つです。
利益の多寡により税率がかわりますが、3つあわせて、だいたい利益の30%ほどになります。
ちなみに、この税金に、消費税はふくまれません。
税込み経理をしているときは、租税公課として経費に計上されます。
いっぽう、税抜き経理をしているときは、実質的に経費になっています。
そのときの利益は、税抜き状態ですから。
配当金
利益からは、さらに配当金がでていくこともあります。
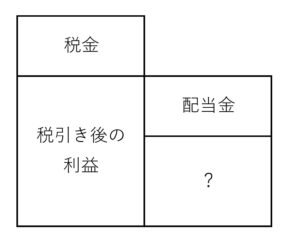
この配当は、上場でもしていなければ、あまり行われないものです。
というのも、配当をしても、経費にならないからです。
つまり、税金がへらないのです。
もし経費になるとすれば、配当金は経費の性格になじみません。
経費とは、売上をあげるためのものですから。
いっぽうの配当金とは、「もうかったから株主にも分配するよ」というものです。
そんなわけで、配当は、税金をはらった残りの利益からおこなうのです。
内部留保
利益から、税金・配当金をはらったのこりを、内部留保といいます。
利益のうち、会社にのこす=留保する…という意味あいです。
(内部留保とは、会社にのこっているお金をいうのではありません)
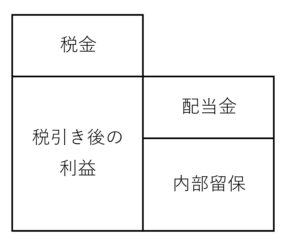
この内部留保をつかい、さらなる仕入れをしたり、経費をつかったりして、つぎの売上につなげていきます。
もし黒字がつづくのなら、内部留保もふえていきます。
すると、事業のためにつかえるお金もふえる…とは限らないのが、会計のむずかしいところです。
…とはなしを続ける前に、借入金の元本返済について確認しておきましょう。
(参考)借入金の元本返済
借入金の元本返済は、利益からおこなう…とかんがえます。
というのも、元本の返済は、経費にならないからです。
もし、借入れをしたときに収入になるなら、元本の返済も経費になるべきです。
ただ、借入れをしたものの、つかわずに残しておくこともあるでしょう。
すると、かりに収入になるとすれば、税金がかかってしまいます。
借りただけなのに。
というのも理不尽なので、借入れをしても収入にはなりません。
そのつじつま合わせのため、元本を返済しても、経費にならないのです。
ここで、「返済のためのお金はどうするの…?」という疑問がでてきます。
お金がでていっても、経費にならないわけですから。
その返済は、利益からおこなう…とかんがえます。
利益が「100」なら、お金も「100」ふえるはず。
元本返済が「30」なら、それを「100」からひいて、「70」が残ることになる…
利益と借入返済の関係は、こんなふうになっています。
(利息は経費になります)
もし、元本の返済分だけの利益をだせないと、会社のお金はへっていくことに注意しましょう。
では、内部留保のはなしをつづけます。
会社の利益がどこへいったのか調べる方法
利益(内部留保)のぶん、お金がふえるとは限りません。
たとえば、売り上げたのに、代金をもらうのが翌年度になったとき。
- 今年度……売上のぶん利益はふえるが、お金はふえない
こういうことが起こるわけです。
こうした利益とお金のズレ、つまり利益がどこへいったのかを調べるには、算数的な見方をします。
このときつかうのが、貸借対照表です。
(利益は、純資産である利益剰余金にふくまれます)
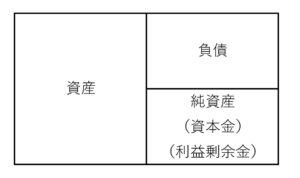
この貸借対照表は、左右の合計が、かならず一致します。
- 資産=負債+純資産
この算式を、応用していくのです。
もし、利益(純資産)がふえるなら、つじつま合わせでつぎのことが起こります。
左右のバランスをとるために。
- 資産がふえる
- 負債がへる
たとえば、利益とおなじだけ、資産がふえることもあります。

あるいは、利益とおなじだけ、負債がへることもあります。
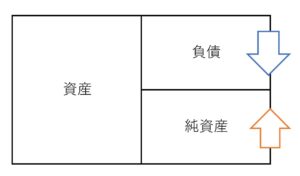
さて、ここから難しくなります。
というのも、お金だって増減するからです。
サンプルをつかって、みていきましょう。
- 利益「100」なのに、お金は「30」しかふえていない
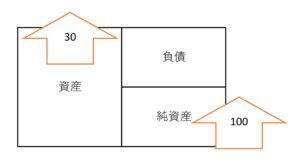
このときは、左右の合計は一致していません。
なので、つじつま合わせが必要です。
たとえば考えられるのは、資産が追加で「70」ふえる。
すると、左右の合計は一致するので。
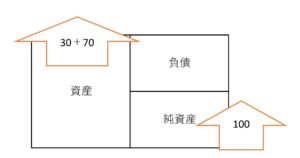
あるいは、負債が「70」へる。
これでも、左右の合計は一致します。
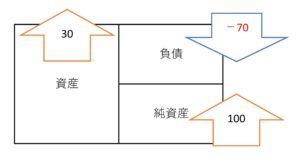
ただ、現実はむずかしいもの。
ここまで単純なケースは、まずありません。
貸借対照表の、すべての項目の「増減」を洗い出していくことになります。
でも、こうすれば、会社の利益がどこへ行ったのかは、分かります。
そのときは、お金と利益のズレについて、つぎのような結論が導き出されます。
- お金がふえる代わりに、○○が増減した
- お金がへる代わりに、○○が増減した
すると、なぜ○○は増減したのか…という疑問もでてきます。
それは、経営判断の結果です。
もし、〇〇の増減がねらったものなら、それもよし。
いっぽう、そうでないなら、つぎは判断や行動を変えていかなければなりません。
数字と経営は、このあたりでリンクしてくるのです。
大事なのは「増減」です。
貸借対照表が1つしかないなら、増減はわかりません。
2期分を用意するか、試算表も活用してみましょう。
せっかく稼いだ利益がどこへいったのかが分からなければ、稼ぎがいもないですから。
また、それが分かれば、今後のヒントにもなりますし。
お金のつかいかたの。
まとめ
会社の利益がどこへいったのか調べる方法について、みてきました。
カギになるのは、貸借対照表と増減です。
事業をしていると、どうしても次のようなことがおこります。
- 黒字なのに、みあったお金がふえていない
- 赤字なのに、お金がふえている…?
こうしたときに原因がわからなければ、根拠のない判断をせざるを得ません。
すると、のちのち困ったことになるかもしれない…
どうやって利益をかせぎ、かせいだ利益をどうつかうか。
このサイクルは、事業をやめるまでつづきます。
であれば、かせいだ利益がどこにあるかは突き止めておきましょう。
自分が納得できる判断をするために。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。


