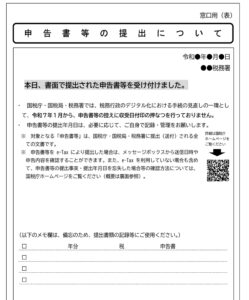経営者ならいつも押さえておきたい経理に関する3つのこと
経営者の仕事は、判断をすることです。
その判断の根拠に数字もあるために、押さえておきたいことをみていきましょう。
経営者の仕事とは
経営するとは、判断をするということです。
- いまどうするか…?
- もし、いまが上手くいっていないなら、どう変えていくか…?
こうした判断をつみかさねていくのが、経営者の仕事なわけです。
その判断をするときの根拠には、いろんなものがあります。
「なぜ、それをするのか…?」
こう聞かれたときに、シンプルに「やってみたいから」というのも、よいかもしれません。
あるいは、直感。
義務…ということも、あるかもしれませんね。
ときには、好き嫌いや義理ということも。
いずれにしても、経営の目的には、お金を稼ぐこともふくまれます。
そのお金は、数字で表現・管理されるもの。
であれば、経営判断も、数字やお金の要素にもとづいていることが必要だとおもうのです。
いつも押さえておきたい3つのこと
経営判断をするためには、つぎの3つのことも押さえておきましょう。
- 儲かっていて、かつ、お金もあるか
- 借入金は返せるか
- 将来はどうなるか
儲かっていて、かつ、お金もあるか
儲かっているのに、お金が足りない…ということがあります。
これを、「勘定合って銭足らず」といったりもします。
その反対に、儲かっていないのに、なぜかお金があることもあります。
こうしたことが起こるのは、会計のルールが原因です。
儲け(利益)の計算は、お金ではなく、モノやサービスの移動にもとづいておこなわれるからです。
たとえば収入。
収入は、商品を引き渡したり、サービスの提供が終わったときに、利益の計算にくみこまれます。
このときに、もしお金を受けとっていなければ、利益はでているのに、お金はない…
こんな状況になります。
いっぽう経費についても、仕組みはおなじです。
お金は払っていないのに、経費が存在する…ということもあるのです。
こうしたことは、稀におこる例外ではなく、むしろ、これがスタンダードです。
利益とお金の増減には、いつもズレがあるのです。
これを押さえておかないと、「つかってはいけないお金をつかってしまった…」ことの原因にもなってしまいます。
(利益とお金の増減は最終的には一致しますが、そこまでには長い時間がかかります)
利益は、損益計算書にのっています。
いっぽうお金は、貸借対照表にのっています。
残高だけではなく、これから入ってくるもの(売掛金など)や出ていくもの(買掛金など)も含めて。
ただ、貸借対照表だと増減はわからないので、試算表のほうがよいかもしれません。
損益計算書と貸借対照表。
すくなくともこの2つは、定期的にみておきましょう。
借入金は返せるか
事業は、基本的に、支払いができなくなったときに終わってしまいます。
ときに、支払いを待ってくれないケースもあるので。
その支払いの一つに、借入金の返済もふくまれます。
この借入金の返済(元本のぶぶん)は、経費にはなりません。
借入れをしたときに、収入にならないからです。
借入れをしたのに収入になるなら、税金がかかってしまいますから…
たとえば、返済額が「100」だったとしましょう。
- もし利益が「150」だったら、返済で「100」つかうので、手元には「50」残ります
いっぽう…
- もし利益が「80」だったら、返済で「100」つかうので、「20」足りないことになります
このとき、前期から繰りこされたお金があれば、「足りない」を回避できるかもしれません。
利益の計算は年度ごとにおこなうので、年度がはじまるときには、お金をもっているはず…
そのお金が、前期から繰りこされたお金です。
こういう仕組みになっているので、返済額だけの利益をださなければならない…とかんがえます。
それが達成できなければ、お金が足りなくなる原因にもなるので。
借入れをしているなら、元本返済額以上の利益をめざしましょう。
なお、社長が経費を立て替えることも、あるかもしれません。
この立て替えは、社長からみたときのこと。
会社からみれば、借入れです。
あるとき払いの催促無し…というケースがほとんどですが、いずれは返さなくてはなりません。
このことも織り込んで、利益をみるようにしましょう。
将来はどうなるか
せっかく事業をするなら、なんらかの目標もあろうかと思います。
その目標にちかづいているのか…
あるいは、目途がたっていないのか…
こうしたことは、お金や数字の状況からわかることもあります。
たとえば、次の視点ももってみましょう。
- このままいくと、今期はどうなりそうか…?
会計ソフトをつかっているなら、クリックひとつで「推移表」をみることができます。
そこには、月ごとの利益の実績だけが、記載されているはずです。
なので、Excelに変換するなどして、空欄になっている将来のところに数字をいれてみましょう。
自分なりに、現実的な数字を。
すると、つぎの決算がどうなりそうか…は、なんらかの目途がつくはずです。
将来はどうなるかわからない…という前提であっても。
大事なのは、「その数字をみたときにどう思うか」です。
もしかしたら、なにも感想などもたないかもしれません。
あるいは、「もっと…」とか「変えたい」という感想もあるかもしれません。
ただ、その思い次第で、行動はかわっていくはずです。
数字がきっかけで、行動がかわるかもしれない。
数字を経営に活用する…とは、こういうことでもあるのです。
まとめ
経営者なら、いつも次のことは、数字の根拠とともに押さえておきましょう。
- 儲かっていて、かつ、お金もあるか
- 借入金は返せるか
- 将来はどうなるか
「いつも」とは書きましたが…
いつもいつも、数字にがんじがらめにされているような状態がよいわけではないです。
人間ですから。
でも、数字もなんらかのきっかけになり得ることは、知っておきましょう。
数字も、大事な道具なのです。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。